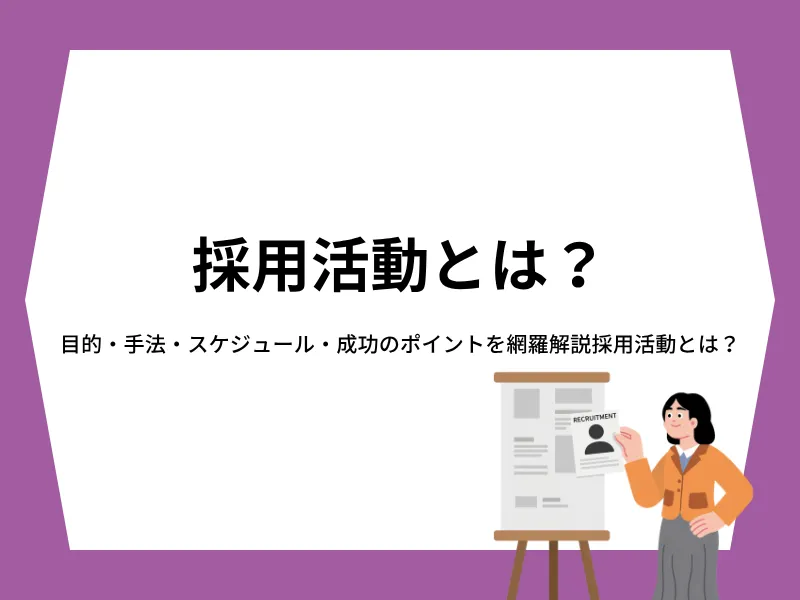採用手法
採用方法
2026.1.21
ジョブ型雇用とは?導入背景から企業事例・メリット・進め方まで徹底解説
この記事の監修者:
株式会社アズライト 佐川稔

「優秀な若手の離職が止まらない」「一律の評価制度に現場が疲弊している」といった課題に直面していませんか?
その背景には、従来の「メンバーシップ型」雇用の限界があるかもしれません。
そこで注目されているのが、職務を明確に定義する「ジョブ型雇用」です。テレワークの普及や高度人材の争奪戦を受け、日立や富士通など多くの有力企業がこの制度への転換を加速させています。
本記事では、ジョブ型雇用の基礎知識からメリット・デメリット、大手企業の導入事例、そして具体的な制度設計の6ステップを網羅的に解説します。自社の風土を活かしつつ、専門性を最大化させる「日本型ジョブ型雇用」を実現するヒントとして、ぜひご活用ください。
- ジョブ型雇用とは
- ジョブ型雇用が注目されている理由
- 経団連会長によるジョブ型雇用推進
- テレワークの普及の影響
- 専門職・業種の人手不足
- 有力企業によるジョブ型雇用導入の本格化
- ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用の違い
- ジョブ型雇用のメリット
- スキル・技術のある人材を確保できる
- 成果に応じて正当に社員を評価できる
- 業務内容に合致した人材を採用できる
- ジョブ型雇用のデメリット
- 早期転職・離職の可能性がある
- 流動的な人材の活用が難しい
- 給与体系・評価項目などの抜本的な見直しが必要
- ジョブ型雇用を導入している企業事例
- 株式会社日立製作所
- ソニーグローバルソリューションズ株式会社
- 株式会社資生堂
- 富士通株式会社
- KDDI株式会社
- ジョブ型雇用の導入ステップ
- ジョブ型雇用を適用する範囲を検討する
- 職務記述書(ジョブディスクリプション)を作成する
- 職務記述書をもとに評価を測定する
- 職務価値を数段階の等級に区分する
- 等級に応じた賃金を設定する
- 職務記述書や職務価値を定期的に見直す
- ジョブ型雇用のまとめ
ジョブ型雇用とは

ジョブ型雇用とは、職務内容に対して最適な人材を割り当てる雇用形態のことです。あらかじめ「ジョブディスクリプション(職務記述書)」によって、仕事の内容、責任の範囲、必要なスキル、勤務地などが詳細に定義されます。
欧米では一般的なスタイルであり、企業は「その仕事ができる人」を採用し、労働者は「自分の専門スキル」を対価に報酬を得ます。
日本の主流である「まず人を採用し、後から仕事を割り振る」スタイルとは異なり、組織の「役割(ポスト)」を埋めるために、最適なスペシャリストを配置する考え方です。
ジョブ型雇用が注目されている理由

日本において長年主流だったメンバーシップ型雇用が見直され、なぜ今「ジョブ型」への転換が急務となっているのでしょうか。そこには、社会構造の変化と経済的な必然性が重なり合っています。
ここでは、注目される背景となった4つの主な要因について解説します。
経団連会長によるジョブ型雇用推進
日本最大の経済団体である経団連は、2020年の提言において「日本型雇用の見直し」と「ジョブ型雇用の推奨」を強く打ち出しました。
その背景には、終身雇用や年功序列といった従来の仕組みが、変化の激しい現代では企業の競争力を削ぐ要因になりかねないという強い危機感があります。当時の中西宏明前会長は「一括採用や終身雇用はもはや限界」と明言し、専門性を軸とした評価への移行を呼びかけました。
この提言は、ジョブ型雇用を単なる「外資系の制度」から、日本企業が生き残るための「経営戦略」へと押し上げる大きな転換点となりました。
テレワークの普及の影響
新型コロナウイルスの流行に伴うテレワークの浸透は、マネジメントのあり方を根本から変えました。
これは、オフィスで顔を合わせる環境では、仕事への姿勢や残業時間といった「プロセス」による評価が成立していましたが、遠隔業務では労働実態が見えにくくなったためです。
こうした環境下で、個々の業務範囲と責任を明確にするジョブ型の考え方が改めて注目されました。「働いた時間」ではなく「成果」で評価する仕組みは、リモート環境における公平な人事評価と生産性向上に直結します。
この「目に見えない労働」を管理する手法への転換が、日本企業においてジョブ型導入を後押しする決定的な要因となりました。
専門職・業種の人手不足
深刻化する専門人材の不足を解消するために、ジョブ型雇用の導入は不可欠な戦略となっています。特定のスキルを持つスペシャリストに対し、市場価値に見合った柔軟な処遇を提示できるからです。
従来の日本型雇用では、職務に関わらず年次や役職で給与が決まるため、高度な専門性を持つ個人を特別遇することが困難でした。ジョブ型であれば年齢に関わらず、職務の難易度や希少性に基づいた高待遇が可能になります。
ジョブ型雇用による職務と報酬を直結させる仕組みは、採用競争力を高め、専門人材不足を解決する切り札として期待されています。
有力企業によるジョブ型雇用導入の本格化
日本を代表する大手企業の相次ぐ導入は、ジョブ型雇用が日本全体のスタンダードとなる大きな転換点となりました。
日立製作所や富士通といったナショナルクライアントが、グローバル競争力の強化や「キャリア自律」を掲げて制度を刷新したことで、導入の有効性が証明されたからです。
例えば、日立製作所は全社員を対象に職務記述書を作成し、個人の適性を仕事に合わせる体制を整えました。こうした先行事例がロールモデルとなり、日本企業全体の雇用システムをアップデートする強力な潮流となっています。
ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用の違い
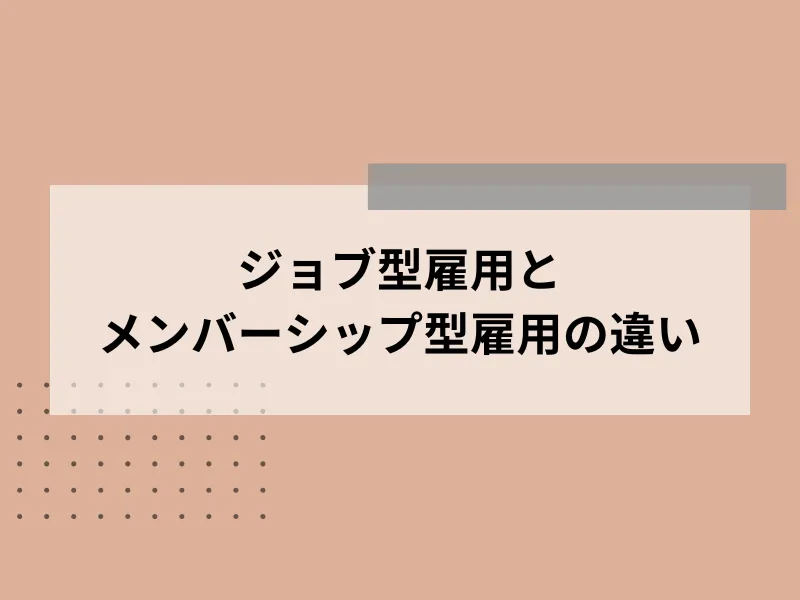
ジョブ型雇用を正しく理解するためには、日本独自の「メンバーシップ型雇用」と比較するのが最も近道です。両者の根本的な違いは、「仕事に人を割り当てる」か「人に仕事を割り当てる」かという点にあります。
比較項目 | ジョブ型雇用 | メンバーシップ型雇用 |
|---|---|---|
考え方 | 仕事に人を割り当てる | 人に仕事を割り当てる |
採用基準 | 専門スキル・経験(即戦力) | ポテンシャル・適応力 |
職務内容 | ジョブディスクリプションで限定 | 会社主導で決定(無限定) |
異動・転勤 | 原則なし(本人の同意が必要) | 会社の命令で発生する |
評価・報酬 | 職務の完遂度や成果 | 年次や能力など属人的な要素 |
主な対象 | 特定分野を極めるスペシャリスト | 幅広い経験を積むゼネラリスト |
経営者や人事担当者からすれば、「ジョブ型とメンバーシップ型のどっちがいい?」と議論が絶えませんが、一概にどちらかが優れているわけではありません。大切なのは、自社の事業成長や組織のフェーズに合わせて、両者の長所をいかに組み合わせるかです。
ジョブ型雇用のメリット
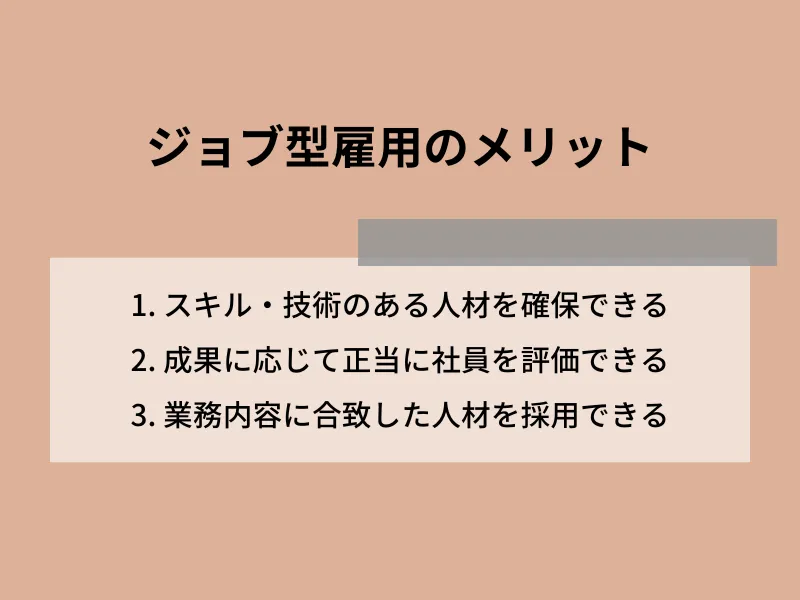
ジョブ型雇用を導入することで、企業は従来のメンバーシップ型では難しかった「専門性の高い組織づくり」が可能になります。
ここでは、企業が享受できる主な3つのメリットを解説します。
スキル・技術のある人材を確保できる
ジョブ型雇用の大きな利点は、高度な専門スキルを持つ人材を戦略的に獲得・維持しやすくなることです。職務と報酬が直結しているため、一律の給与体系に縛られず、市場価値に基づいた柔軟な処遇決定が可能になるためです。
例えば、DX推進に不可欠なAIエンジニアやデータサイエンティストに対し、年功序列の枠を超えた条件を提示することで、外資系やベンチャー企業との人材争奪戦においても優位に立てます。
特定の役割に必要なスペシャリストをピンポイントで確保できるこの仕組みは、企業の技術競争力を左右する重要な鍵となります。
成果に応じて正当に社員を評価できる
評価基準が客観的かつ明確になり、社員の納得感を高められる点も大きなメリットです。ジョブ型雇用では、あらかじめ職務記述書で「達成すべき目標」や「責任範囲」を定義するため、主観を排除した成果ベースの評価が可能になります。
これにより、従来の日本型雇用で起こりがちだった「上司への忖度」や「長時間労働の自負」といった曖昧な評価指標の排除が可能です。プロセスの見えにくいテレワーク環境であっても、成果に基づいた公平な格付けが可能になるため、社員の納得感とモチベーションの向上に大きく寄与します。
業務内容に合致した人材を採用できる
評価基準が客観的かつ明確になり、社員の納得感を高められる点も大きなメリットです。ジョブ型雇用では、あらかじめ職務記述書で「達成すべき目標」や「責任範囲」を定義するため、主観を排除した成果ベースの評価が可能になります。
これにより、従来の日本型雇用で起こりがちだった「上司への忖度」や「長時間労働の自負」といった曖昧な評価指標を排除できます。
「頑張っている姿勢」ではなく「出した成果」がダイレクトに給料へ反映される仕組みは、プロセスの見えにくいテレワーク環境においても公平な格付けを可能にし、社員の納得感とモチベーションの向上に大きく寄与するはずです。
ジョブ型雇用のデメリット
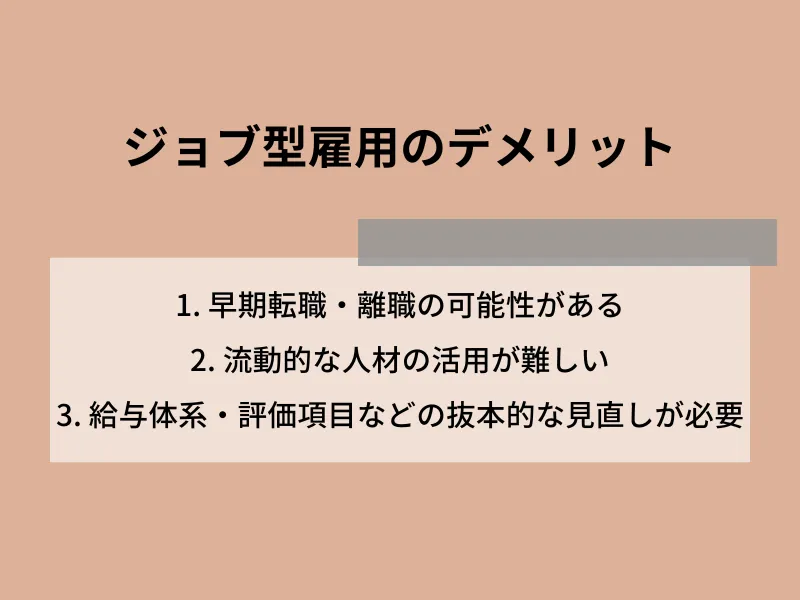
ジョブ型雇用には多くの利点がある一方で、従来の日本型組織にとっては無視できない課題やリスクも存在します。
ここでは、導入時に注意すべき3つのデメリットを解説します。
早期転職・離職の可能性がある
ジョブ型雇用では、専門性を高めた社員が好条件を求めて他社へ流出するリスクが高まります。個人のスキルが社内限定から、どこでも通用する市場価値へと変わるため、転職のハードルが下がるからです。
これまでは「新卒で入社して定年まで勤める」という年功的な前提があり、会社への依存関係で引き留めが可能でした。しかし、ジョブ型では「職務で貢献する」自律的な関係に変わります。
そのため、会社側に独自の魅力がなければ、新卒から育てた若手であっても「ここはスキルアップの踏み台」と割り切り、より高い給料や裁量を提示する他社へ移ってしまう懸念があります。
流動的な人材の活用が難しい
ジョブ型雇用はあらかじめ職務記述書(ジョブディスクリプション)で業務範囲を定義するため、人手不足の部署を他部署が手伝うといった柔軟な対応が困難になります。
「この仕事をする」という契約である以上、異動や配置換えには本人との合意が原則です。メンバーシップ型のように会社主導で人員を動かすことができず、欠員が出た際も既存社員の異動で安易に埋められません。
その結果、不足が出るたびに外部から専門人材を採用し直す手間とコストが発生してしまいます。
給与体系・評価項目などの抜本的な見直しが必要
導入には、これまでの年功序列を前提とした人事制度をゼロから作り直す作業を伴います。「人に給料がつく」仕組みから「ポスト(職務)に給料がつく」仕組みへの大転換が必要だからです。
全社員の職務記述書(ジョブディスクリプション)を作成し、市場価値に基づいた報酬・評価基準を策定するには、膨大な時間と労力が削られます。
また、移行期には「今の給料が下がるのではないか」といった既存社員の不安を解消するための対話も不可欠です。管理部門には大きな負担と、組織としての強い覚悟が求められます。
ジョブ型雇用を導入している企業事例

日本を代表する大手企業も、グローバル競争に勝ち抜くために相次いでジョブ型雇用へ舵を切っています。これら導入企業の多くは、単に海外の仕組みを真似るのではなく、自社の経営戦略に合わせて制度を最適化しているのが特徴です。
ここでは、先行して変革を進める代表的な5社の事例を紹介します。
株式会社日立製作所
2008年の巨額赤字を機に「社会イノベーション事業」へ舵を切った日立製作所は、世界共通の尺度で人財を「見える化」するため、国内のジョブ型雇用を牽引してきました。
2021年までにほぼ全社員の職務記述書(ジョブディスクリプション)を作成し、2026年度からは新卒採用も「ジョブ型」へ完全移行する予定です。学生はエントリー時に希望職種を選べるようになり、入社直後から専門性を活かした自律的なキャリア形成が可能です。
また、学習支援や社内公募も拡充し、社員が自らの意志で成長し、適正な評価と給料を得られる仕組みを整備しています。個の力を引き出すことで、グローバル市場での競争力を高めています。
ソニーグローバルソリューションズ株式会社
ソニーグループは「個」の強みを活かすため、早くからジョブ型を導入しています。2015年からは「現在の役割」を基準とした「ジョブグレード制度」を運用し、報酬は役割と成果に基づいて決定されます。
等級は「I等級群」と「M等級群」に分かれ、その時々の役割に応じてシームレスに行き来できるのが特徴です。職務内容やスキルが詳細に定義されているため、社員は新卒時から自律的なキャリアを意識しやすくなっています。
また社内公募制度も活発で、会社主導の異動を待たず、自らの専門性を武器に望むポストへ挑戦し、高い給料や成長を勝ち取れる文化が定着しています。
株式会社資生堂
資生堂は2021年、国内の管理職および総合職を対象にジョブ型人事制度へ移行しました。評価の軸を個人の「能力」から「職務(ジョブ)」へ移すことで、グローバル基準に沿った客観的な処遇を実現しています。
導入の背景には、国籍や年齢を問わず、実力がある若手を早期抜擢できる環境を整える狙いがあります。職務内容と必要な専門性を明確にしたことで、「今の仕事がどう給料に反映されるか」がクリアになり、社員のキャリア自律を力強く後押ししているのが特徴です。
新卒からベテランまで、個々の専門性が正当に評価される仕組みを構築し、美のイノベーションを生み出し続ける組織へと進化を遂げています。
富士通株式会社
富士通は「IT企業からDX企業へ」の変革を掲げ、2022年までに国内グループ全社員約45,000人へジョブ型人事制度を導入しました。
職務記述書(ジョブディスクリプション)で職責の重さを定義し、役割に応じた報酬水準を設定することで、従業員の主体的な挑戦を促しています。
さらに2026年度からは、新卒採用を「ジョブ型」へ完全移行することを発表しました。有償インターンシップの拡充などを通じ、入社時から専門性を発揮できる環境を整備しています。
年功序列を廃し、成果がダイレクトに給料へ反映される仕組みに切り替えたことで、グローバルで通用する高度な人材の確保と、機動力のある組織づくりを加速させています。
KDDI株式会社
KDDIは、市場価値に基づいた評価と報酬を実現する「KDDI版ジョブ型人事制度」を推進しています。一律の導入ではなく、日本の雇用の良さである安定を残しつつ、成果主義を融合させた点が特徴です。
また、2021年度からは新卒採用においても「ジョブ型採用」を導入しています。初期配属を確約することで、学生時代に培った専門性を入社直後から発揮できる環境を整えています。
さらに、職務の市場価値を報酬に反映させる仕組みにより、高度な専門スキルを持つ人材が正当な給料を得られる体制を構築しました。
社内公募制度の活性化と併せ、社員が自らの意志でキャリアをデザインできる「自律型組織」への転換を強力に進めています。
ジョブ型雇用の導入ステップ
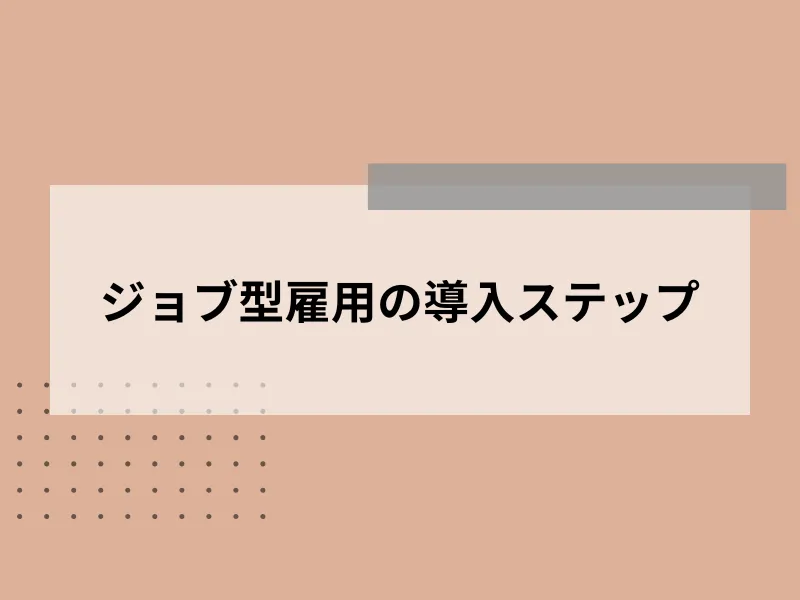
ジョブ型雇用は単なる「評価制度の変更」ではなく、組織のあり方そのものを変えるプロジェクトです。
ここでは、導入にあたって踏むべき6つのステップを解説します。
ジョブ型雇用を適用する範囲を検討する
まずは、自社のどの部署や職種から導入するかを決定します。全社一斉の導入は、現場に大きな混乱を招くリスクがあるため慎重な判断が必要です。
メンバーシップ型からジョブ型への移行は、給料や評価の仕組みを根本から変えるため、全社一斉に進めると既存社員の反発や管理職の負担が一気に噴出しかねません。
そのため、人材獲得競争が激しい「DX部門」や「高度専門職」など、限定的な範囲からスモールスタートするのが現実的です。特定の部署で成功事例を作り、運用のノウハウを蓄積してから段階的に広げることで、組織全体へのスムーズな浸透が可能になります。
職務記述書(ジョブディスクリプション)を作成する
続いて、ジョブ型の土台となる「職務記述書(ジョブディスクリプション)」を作成します。各ポストの目的や具体的な業務、責任の範囲、必要なスキルなどを詳細に言語化する作業です。
この書類は、採用や評価における「唯一の基準」となります。現場の実態とズレが生じないよう、人事だけで完結させず、各部署のマネージャーと対話を重ねて一項目ずつ丁寧にすり合わせることが不可欠です。
【定義すべき項目例】
職務の目的(ミッション)
主な業務内容
責任の範囲・権限
必要なスキル・経験
待遇・福利厚生
職務記述書をもとに評価を測定する
作成した職務記述書を基準に、個人の能力や年次ではなく「職務における成果や責任」を評価します。
客観的な測定手法として、厚生労働省は以下の4つを挙げています。
単純比較法:職務全体を比較し、難易度順に並べる
分類法:決めておいた等級定義に各職務を当てはめる
要素比較法:基準職務と比較し、責任やスキルごとに評価する
要素別点数法:職務を要素分解し、点数化して合計する
主観的な評価を排し、職務記述書で定義したミッションへの貢献度を客観的に測定することが重要です。基準が明確になれば、新卒からベテランまでが納得感を持って働ける土壌が整います。
職務価値を数段階の等級に区分する
測定した職務の重み(重要度や難易度)に基づき、数段階の「等級(グレード)」に格付けします。
ここでも「人」ではなく「仕事」そのものを評価するのがポイントです。例えば、同じ「部長」という肩書きでも、統括する範囲や必要な専門性によって等級を分けるなど、職務価値に応じた公平なランク付けを行います。
なお、等級の「数」には注意が必要です。区分が粗すぎると個々の貢献を正当に評価しにくくなり、逆に細かすぎると、運用の手間が増えるだけでなく、柔軟な人事異動を阻害する要因にもなります。自社の組織規模に適した、バランスの良い階層設計が求められます。
等級に応じた賃金を設定する
決定した等級に基づいて、具体的な報酬額を設定します。
ジョブ型において重要なのは、社内バランスだけでなく、外部の労働市場における「市場相場」を基準にすることです。競合他社に負けない水準の給料を設定することで、外部からの優秀な人材獲得を有利にし、社内エースの流出を防ぐ「防波堤」としての役割を持たせます。
専門性の高い職務には、年次に関わらず高い報酬を提示できる仕組みを整えましょう。「人に給料がつく」年功序列から、「ポストの価値に給料がつく」仕組みへの完全な転換が、優秀な人材の獲得・引き留めを確かなものにします。
職務記述書や職務価値を定期的に見直す
ジョブ型雇用は「一度作れば終わり」ではありません。市場環境や事業戦略が変化すれば、求められる職務内容やその価値も刻々と変わるからです。
そのため、職務記述書の内容や等級が現状に即しているかを定期的にメンテナンスし、常に最新の状態へアップデートし続ける仕組みを整えましょう。
この継続的な改善こそが、形骸化を防ぎ、組織の機動力を維持し続ける鍵となります。現場と人事が対話を止めず、変化に柔軟に対応し続ける姿勢が、ジョブ型を成功に導く土台となります。
ジョブ型雇用のまとめ
ジョブ型雇用への移行は、企業と社員の関係を「依存」から「自律」へ変える大きな挑戦です。導入には職務記述書の作成などの実務負担もありますが、専門人材を確保し個の力を引き出す仕組みは、現代の競争を勝ち抜くために不可欠です。
大切なのは海外の手法をそのまま導入するのではなく、先行事例を参考に自社の文化に合わせた「日本版」を模索することです。まずは特定部署からスモールスタートし、現場との対話を重ねて制度を育てましょう。
社員が専門性を武器に自律し、会社がそれを正当な報酬で支える。この「選び合う関係」こそが、組織の機動力と持続的な成長を支える源泉となります。
自社では難しいと感じた場合は、人材採用のプロであるアズライトに相談しましょう。ジョブ型雇用やジョブディスクリプションについて的確にアドバイスしてくれます。

この記事の監修者
株式会社アズライト 佐川稔
株式会社アズライト代表取締役。採用がうまくいかない優良企業を採用できる企業へ改革するために、戦略・運用に特化した採用コンサルティングファーム「株式会社アズライト」を創業。キャリアに悩む方々のために就活・転職相談BAR「とこなつ家」を池袋にて共同経営中。
関連記事